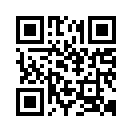2008年03月04日
活動取材レポート
事務局が取材したアクションチームの活動レポートをご紹介
 今までに取材したチームはこちら!
今までに取材したチームはこちら!
・フォーラムまきのはら(7/7)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・WAKUWAKU西郷(7/10)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・森水人のネットワーク(9/3)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・エコピュア佐久間(9/9)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・夢遊研究所(9/9)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・株式会社ノースエネック(9/22)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・静清信用金庫(9/29)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
****************************************
****************************************

 今までに取材したチームはこちら!
今までに取材したチームはこちら!・フォーラムまきのはら(7/7)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・WAKUWAKU西郷(7/10)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・森水人のネットワーク(9/3)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・エコピュア佐久間(9/9)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・夢遊研究所(9/9)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・株式会社ノースエネック(9/22)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
・静清信用金庫(9/29)
└ 取材レポート
└ エントリー内容
****************************************
****************************************
2007年10月06日
活動取材:エコピュア佐久間
今回は、佐久間町浦川(浜松市天竜区)で活動している「エコピュア佐久間」
に取材に行ってきました。
袋井から天竜川沿いに上っていき、
佐久間町の中心街を抜けたところに「遊学体験農園」があります。
目的地に着くと、さっそくのぼり旗を発見!

“「地にいのち、子供に未来を」遊学体験農園エコピュア佐久間”
畑の方をのぞいてみると、作業をしている方たちを見つけました。
声をかけると、金森喜久代さんが来てくださいました。

「今日はね、大根の種まきで近所の子供たちも来てくれたんですよ」
浦川地区の小学校は1学年5人ほど。今回は10人ほどが集まっていました。
年に3回、長いもやとうもろこし、大根などの種まきと収穫を行うそうです。

「佐久間の浦川地区26世帯から回収した生ごみを堆肥にして、野菜などを育ててるんです」
と、金森さんが指さしたのは生ごみのコンポスト。

その回収を「エコピュア佐久間」の会員さんが毎週月曜日に行っているそうです。
1回で回収する量は多い時で150kgほど。
金森さんが活動を始めたのは平成5年。
キッカケはニュースなどで耳にする情報でした。
・生ごみを埋める場所がなく、焼却している。
・大量に焼却するとその分のCO2が発生し、地球温暖化につながる。
「このままでは大変なことになる。どうにかしなくでは」
そう考えた金森さんが佐久間町のごみの現状を調べると、
一家庭のごみの処理に1年に1万円もかかっているとのこと。
どうにかならないものか。
そこで「ボカシ」のことを勉強し、生ごみを堆肥化して野菜を
育てる取り組みを思いついたそうです。
町内の生ごみを回収して堆肥化すれば、町費の節約にもなり、
子どもたちに安全な野菜を食べさせることもできる。
そんな思いから今の活動にいたったとのこと。
「おうちでね、自分で堆肥化してる人もいるんだけど、
土地がなかったりで、できない人たちもいるからね。
そういう家庭の分を回収してるんですよ」
と、今までの回収の記録をつけたノートを見せてくださいました。
毎回分、きっちりと記入されてました。活動を始めた当初から
ずっと記帳しているそうです。
「さぁ、種まきが終わったらみんなで畑にネットをかけるよ。
こうするとカラスに食べられなくてすむからね」

みんなで協力してネットをかけ、今日の作業は終了。
その後には素敵なごほうびが待っていました。
「ブルーベリーだ!」
「ヨーグルトわたしだいすき!!」

ヨーグルトに同じ農園でとれたブルーベリーをいれて食べました。
金森さんからブルーベリーのお話の絵本を読んでもらい、
子どもたちもすっかり満足顔でした。
こんな子どもたちの笑顔が活動の源になっているのかもしれません。
今回、植えた大根の収穫祭は11月24日(土)。
大根がおでんに変身して登場するそうです。

エコピュア佐久間のみなさん、
子どもたちの未来のためにがんばってください!
チーム名:エコピュア佐久間(no.198)
活動タイトル:“地に生命、子供に未来を”!!
に取材に行ってきました。
袋井から天竜川沿いに上っていき、
佐久間町の中心街を抜けたところに「遊学体験農園」があります。
目的地に着くと、さっそくのぼり旗を発見!
“「地にいのち、子供に未来を」遊学体験農園エコピュア佐久間”
畑の方をのぞいてみると、作業をしている方たちを見つけました。
声をかけると、金森喜久代さんが来てくださいました。
「今日はね、大根の種まきで近所の子供たちも来てくれたんですよ」
浦川地区の小学校は1学年5人ほど。今回は10人ほどが集まっていました。
年に3回、長いもやとうもろこし、大根などの種まきと収穫を行うそうです。
「佐久間の浦川地区26世帯から回収した生ごみを堆肥にして、野菜などを育ててるんです」
と、金森さんが指さしたのは生ごみのコンポスト。
その回収を「エコピュア佐久間」の会員さんが毎週月曜日に行っているそうです。
1回で回収する量は多い時で150kgほど。
金森さんが活動を始めたのは平成5年。
キッカケはニュースなどで耳にする情報でした。
・生ごみを埋める場所がなく、焼却している。
・大量に焼却するとその分のCO2が発生し、地球温暖化につながる。
「このままでは大変なことになる。どうにかしなくでは」
そう考えた金森さんが佐久間町のごみの現状を調べると、
一家庭のごみの処理に1年に1万円もかかっているとのこと。
どうにかならないものか。
そこで「ボカシ」のことを勉強し、生ごみを堆肥化して野菜を
育てる取り組みを思いついたそうです。
町内の生ごみを回収して堆肥化すれば、町費の節約にもなり、
子どもたちに安全な野菜を食べさせることもできる。
そんな思いから今の活動にいたったとのこと。
「おうちでね、自分で堆肥化してる人もいるんだけど、
土地がなかったりで、できない人たちもいるからね。
そういう家庭の分を回収してるんですよ」
と、今までの回収の記録をつけたノートを見せてくださいました。
毎回分、きっちりと記入されてました。活動を始めた当初から
ずっと記帳しているそうです。
「さぁ、種まきが終わったらみんなで畑にネットをかけるよ。
こうするとカラスに食べられなくてすむからね」
みんなで協力してネットをかけ、今日の作業は終了。
その後には素敵なごほうびが待っていました。
「ブルーベリーだ!」
「ヨーグルトわたしだいすき!!」
ヨーグルトに同じ農園でとれたブルーベリーをいれて食べました。
金森さんからブルーベリーのお話の絵本を読んでもらい、
子どもたちもすっかり満足顔でした。
こんな子どもたちの笑顔が活動の源になっているのかもしれません。
今回、植えた大根の収穫祭は11月24日(土)。
大根がおでんに変身して登場するそうです。
エコピュア佐久間のみなさん、
子どもたちの未来のためにがんばってください!
チーム名:エコピュア佐久間(no.198)
活動タイトル:“地に生命、子供に未来を”!!
2007年09月13日
活動取材:森水人のネットワーク
今回、取材したのは富士宮で活動する「森水人のネットワーク」。
巻き枯らし指導会員を育成する作業イベントにお邪魔させていただきました。
「ご存知の通り、富士宮には下草の生えていない放置森林がたくさんあります。
この森を健全に育てるためには、人の手を入れる必要があります」
と語るのは森水人のネットワーク代表の大西義治さん。

-巻き枯らし間伐とは-
木の樹皮をむき、立ち枯れの状態にすることで間伐効果を出す近年注目の間伐手法。
木の根元にぐるりと鋸で切れ目を入れて、切れ目から上に向かって
皮をむいていくという、誰にでもできる簡単な作業です。
1年ほどで葉が枯れ落ち、暗かった森に光が差し込むことで、
荒れた人工林を下草の生えた豊かな森にしていくことが出来ます。
同ネットワークでは「日本の森は、こどもが変える」プロジェクトの
環境学習の一環として巻き枯らし間伐体験を、地元などの小中学校やボーイスカウトに
提案しています。
その時に子どもたちの作業のサポートをすることができる指導会員を育成しようと
いうのが今回の取り組み。これが第1回目の研修とのこと。
今回は6名の方が参加。
ひとりひとりに軍手とノコギリ、そして竹製のヘラが渡され、
さぁ、実習開始です。

最初は簡単な講義から。
「まず、木の根元にぐるりとノコギリで切れ目をいれてください。
そのあとは、ヘラで木の皮を上に向かってむいていきます」
と、黙々と実践する大西さん。
「30cmほどむけば、もうそれで立ち枯れするんですけどね。
あとで間伐材として利用しやすいように、なるべく上までむいてください。
15mくらいむいていただけると有難いですね(笑)」

最初は苦戦されていた方も何本かこなすうちに
みなさん、軽快に木の皮をベリベリと剥がし、
巻き枯らしのベテランになっていました。

ただ枯れて倒壊した木は腐りやすく乾燥しにくいが、
立ち枯れするとストックヤードも必要なくキレイな状態で
間伐できるとのこと。
立ち枯れした木は5~10年で倒壊するので、その前に間伐して
利用するのがベストだそうです。

「巻き枯らししたとこと、しないとこでは陽の入り方が全然違うんですよ!」
と、熱く語るのは同ネットワークで活動する若林さん。
若林さんが指差す方向(昨年、巻き枯らしした林)と、
まだ巻き枯らししてない林を見比べると、陽の差し方が全然違いました。

(昨年、巻き枯らしした林)

(まだ、巻き枯らししていない林)
「下草の育ち方も全然違うんですよ」
なるほど。言われて見て思わず納得してしまいました。
立ち枯れし始めると葉が育たなくなり、陽の指す部分が増えるのです。
「今日と同じ作業を今月の23~29日の各日にも開催します。
そこでは、もっといろんな人に巻き枯らしを体験したいただきたいですね」と大西さん。
来年のプロジェクトに向けて、現在も参加を受付中とのこと。
未来を担う子どもたちのために、少しでも多くの指導会員が育つといいですね。
森水人のネットワークのみなさん、ありがとうございました!

チーム名:森水人のネットワーク(no.22)
活動タイトル:巻き枯らし間伐材を進め、コードウッドに使う
巻き枯らし指導会員を育成する作業イベントにお邪魔させていただきました。
「ご存知の通り、富士宮には下草の生えていない放置森林がたくさんあります。
この森を健全に育てるためには、人の手を入れる必要があります」
と語るのは森水人のネットワーク代表の大西義治さん。
-巻き枯らし間伐とは-
木の樹皮をむき、立ち枯れの状態にすることで間伐効果を出す近年注目の間伐手法。
木の根元にぐるりと鋸で切れ目を入れて、切れ目から上に向かって
皮をむいていくという、誰にでもできる簡単な作業です。
1年ほどで葉が枯れ落ち、暗かった森に光が差し込むことで、
荒れた人工林を下草の生えた豊かな森にしていくことが出来ます。
同ネットワークでは「日本の森は、こどもが変える」プロジェクトの
環境学習の一環として巻き枯らし間伐体験を、地元などの小中学校やボーイスカウトに
提案しています。
その時に子どもたちの作業のサポートをすることができる指導会員を育成しようと
いうのが今回の取り組み。これが第1回目の研修とのこと。
今回は6名の方が参加。
ひとりひとりに軍手とノコギリ、そして竹製のヘラが渡され、
さぁ、実習開始です。
最初は簡単な講義から。
「まず、木の根元にぐるりとノコギリで切れ目をいれてください。
そのあとは、ヘラで木の皮を上に向かってむいていきます」
と、黙々と実践する大西さん。
「30cmほどむけば、もうそれで立ち枯れするんですけどね。
あとで間伐材として利用しやすいように、なるべく上までむいてください。
15mくらいむいていただけると有難いですね(笑)」
最初は苦戦されていた方も何本かこなすうちに
みなさん、軽快に木の皮をベリベリと剥がし、
巻き枯らしのベテランになっていました。
ただ枯れて倒壊した木は腐りやすく乾燥しにくいが、
立ち枯れするとストックヤードも必要なくキレイな状態で
間伐できるとのこと。
立ち枯れした木は5~10年で倒壊するので、その前に間伐して
利用するのがベストだそうです。
「巻き枯らししたとこと、しないとこでは陽の入り方が全然違うんですよ!」
と、熱く語るのは同ネットワークで活動する若林さん。
若林さんが指差す方向(昨年、巻き枯らしした林)と、
まだ巻き枯らししてない林を見比べると、陽の差し方が全然違いました。
(昨年、巻き枯らしした林)
(まだ、巻き枯らししていない林)
「下草の育ち方も全然違うんですよ」
なるほど。言われて見て思わず納得してしまいました。
立ち枯れし始めると葉が育たなくなり、陽の指す部分が増えるのです。
「今日と同じ作業を今月の23~29日の各日にも開催します。
そこでは、もっといろんな人に巻き枯らしを体験したいただきたいですね」と大西さん。
来年のプロジェクトに向けて、現在も参加を受付中とのこと。
未来を担う子どもたちのために、少しでも多くの指導会員が育つといいですね。
森水人のネットワークのみなさん、ありがとうございました!
チーム名:森水人のネットワーク(no.22)
活動タイトル:巻き枯らし間伐材を進め、コードウッドに使う
2007年08月23日
活動取材:WAKU WAKU 西郷
今回取材したのは、掛川市の西郷地区で“ソーラー大作戦”に取り組むNPO法人WAKUWAKU西郷。
理事長を務める松浦昌巳さんにお話を伺いました。
-“ソーラー大作戦”とはどういった取り組みですか?
「西郷地区で回収した古紙の収益金で西郷小学校に太陽光発電を設置しようと考えているんです。
月に1回、古紙回収の日があり、約1600世帯分の古紙が集まってきます」

-なぜ、こういった取り組みを始めたんですか?
「以前にPTA会長を務めていまして、その時に「地域も子どももよくなる」取り組みがあればと思ったんです。
去年の今頃(7月)にこの取り組みを思いつき、活動を始めました。
ごみの減量はもちろんですが、子どもたちへの地球温暖化やクリーンエネルギーの環境教育にもなりますし、
災害時には西郷小学校を防災拠点として電気の供給を行えればと思っています」

-回収は今年の3月から始められたということですが、地域の皆さんの反応はどうですか?
「行政の回収日とWAKUWAKU西郷の回収日が両方あって、混乱されている時もありましたね。
でも、WAKUWAKU西郷の回収日に出していただければ太陽光発電の資金になりますのでとみなさんにお願いしました。
来年の夏休みくらいには太陽光発電を設置できればと考えてますので、目に見える形になれば、また少しは理解が得られていくと思います」

-太陽光発電の取り組みは桜が丘中学校区でも行ってますよね?
「そうなんです。そちらの取り組みをしている“エコ桜が丘”の理事長が松下先生といって、私の中学の担任だったんです。
その松下先生がされている活動を西郷でもできないかと思い、始めました」
-素敵なつながりですね!もっとこういった活動が拡がっていくといいですね。
「はい、市の方にも色々とご協力して頂いたのですが、掛川市で桜が丘に続く活動がなかなか出てこなかったそうなので、期待されているようです。また、次に続いてくださる地区があるうれしいですね」
掛川が太陽光発電の街と言われる日も近いかもしれませんね。
松浦さん、今日はありがとうございました!
チーム名:WAKU WAKU 西郷(no.29)
活動タイトル:ソーラー大作戦
理事長を務める松浦昌巳さんにお話を伺いました。
-“ソーラー大作戦”とはどういった取り組みですか?
「西郷地区で回収した古紙の収益金で西郷小学校に太陽光発電を設置しようと考えているんです。
月に1回、古紙回収の日があり、約1600世帯分の古紙が集まってきます」
-なぜ、こういった取り組みを始めたんですか?
「以前にPTA会長を務めていまして、その時に「地域も子どももよくなる」取り組みがあればと思ったんです。
去年の今頃(7月)にこの取り組みを思いつき、活動を始めました。
ごみの減量はもちろんですが、子どもたちへの地球温暖化やクリーンエネルギーの環境教育にもなりますし、
災害時には西郷小学校を防災拠点として電気の供給を行えればと思っています」
-回収は今年の3月から始められたということですが、地域の皆さんの反応はどうですか?
「行政の回収日とWAKUWAKU西郷の回収日が両方あって、混乱されている時もありましたね。
でも、WAKUWAKU西郷の回収日に出していただければ太陽光発電の資金になりますのでとみなさんにお願いしました。
来年の夏休みくらいには太陽光発電を設置できればと考えてますので、目に見える形になれば、また少しは理解が得られていくと思います」
-太陽光発電の取り組みは桜が丘中学校区でも行ってますよね?
「そうなんです。そちらの取り組みをしている“エコ桜が丘”の理事長が松下先生といって、私の中学の担任だったんです。
その松下先生がされている活動を西郷でもできないかと思い、始めました」
-素敵なつながりですね!もっとこういった活動が拡がっていくといいですね。
「はい、市の方にも色々とご協力して頂いたのですが、掛川市で桜が丘に続く活動がなかなか出てこなかったそうなので、期待されているようです。また、次に続いてくださる地区があるうれしいですね」
掛川が太陽光発電の街と言われる日も近いかもしれませんね。
松浦さん、今日はありがとうございました!
チーム名:WAKU WAKU 西郷(no.29)
活動タイトル:ソーラー大作戦
2007年07月25日
活動取材:フォーラムまきのはら環境グループ
夏だ!海だ!お祭りだ!!
ということで、やってきました『スタ☆フェス’07』@相良シーサイドパーク。
会場に着くと、さっそく『STOP温暖化アクションキャンペーン』のぼり旗を発見!

このイベントで出展していたのは、STOP温暖化アクションキャンペーンエントリーチーム
でもある“フォーラムまきのはら 環境グループ”のみなさん。
温暖化防止を訴えるパネルや普段の活動の様子を展示していました。
「イベントでの出展は今回が始めてなんですよ」
と語るのは“フォーラムまきのはら”で活動されている澤田文子さん。

「牧之原では12くらいの区があって、そのうち5~6区で資源回収を行っているんです。
そして回収した収益金を保育園や小・中学校に寄付してるんです」
なるほど、つまり環境教育の資金になってるんですね!
新聞・チラシ、ダンボール、雑誌・ざつ紙などを分別回収しているそうです。
澤田さんがお住まいの菅山区では、昨年の8月から2ヶ月に1回の回収日を設け、
今までに約100トンの資源を回収済みとのこと。

しかも、回収するだけではなく、集まった資源をリサイクルできる状態にする作業を
フォーラムまきのはらのメンバーで行っているそうです。
「例えば、携帯の明細書が送られてくる封筒とかありますよね?そこについているビニールの
フィルム、あれがついたままだとリサイクルできないんです。そういったものを、さらに分別する
作業が必要なんですよ」

分別の方法などを広報のお便りに流してもなかなか徹底することは難しいようです。
「牧之原市のゴミ処理費は年間10億円ほどかかっているんです。しかし、その中の35%くらいは
リサイクル可能な紙なんです。捨てればゴミ、しかも処理費用がかかります。
でも、リサイクルすれば子どもたちのための教育資金になるんです」と熱く語る澤田さん。
地域の取り組みが地域の子どもたちに還ってくる、とても素敵な循環(リサイクル)ですね☆
フォーラムまきのはらの皆さん、これからも頑張ってください!

チーム名:フォーラムまきのはら(no.54)
活動タイトル:雑誌減量大作戦を応援する
ということで、やってきました『スタ☆フェス’07』@相良シーサイドパーク。
会場に着くと、さっそく『STOP温暖化アクションキャンペーン』のぼり旗を発見!
このイベントで出展していたのは、STOP温暖化アクションキャンペーンエントリーチーム
でもある“フォーラムまきのはら 環境グループ”のみなさん。
温暖化防止を訴えるパネルや普段の活動の様子を展示していました。
「イベントでの出展は今回が始めてなんですよ」
と語るのは“フォーラムまきのはら”で活動されている澤田文子さん。
「牧之原では12くらいの区があって、そのうち5~6区で資源回収を行っているんです。
そして回収した収益金を保育園や小・中学校に寄付してるんです」
なるほど、つまり環境教育の資金になってるんですね!
新聞・チラシ、ダンボール、雑誌・ざつ紙などを分別回収しているそうです。
澤田さんがお住まいの菅山区では、昨年の8月から2ヶ月に1回の回収日を設け、
今までに約100トンの資源を回収済みとのこと。
しかも、回収するだけではなく、集まった資源をリサイクルできる状態にする作業を
フォーラムまきのはらのメンバーで行っているそうです。
「例えば、携帯の明細書が送られてくる封筒とかありますよね?そこについているビニールの
フィルム、あれがついたままだとリサイクルできないんです。そういったものを、さらに分別する
作業が必要なんですよ」
分別の方法などを広報のお便りに流してもなかなか徹底することは難しいようです。
「牧之原市のゴミ処理費は年間10億円ほどかかっているんです。しかし、その中の35%くらいは
リサイクル可能な紙なんです。捨てればゴミ、しかも処理費用がかかります。
でも、リサイクルすれば子どもたちのための教育資金になるんです」と熱く語る澤田さん。
地域の取り組みが地域の子どもたちに還ってくる、とても素敵な循環(リサイクル)ですね☆
フォーラムまきのはらの皆さん、これからも頑張ってください!
チーム名:フォーラムまきのはら(no.54)
活動タイトル:雑誌減量大作戦を応援する